奥羽本線・東能代~秋田の鉄道旅と、秋田の歴史について、鉄道・観光・歴史に詳しくない方にも、わかりやすく解説してゆきます!
東能代駅(秋田県能代市)を出発
前回で、五能線を南下してきて、
- 東能代駅(秋田県能代市)
に到着しました。

東能代駅(秋田県能代市)

東能代駅(秋田県能代市)
スイッチバックで方向転換
東能代駅はスイッチバック形式の駅のため、東能代駅から秋田方面へ向かうには、方向転換を行います。
また、快速リゾートしらかみ号であれば、一旦スイッチバックをするため、座席の向きが変わることになります。
すなわち、シートの前後を変えないと、後ろを向いたまま列車が進んでしまうことになります。
そのため、たとえ面倒であっても、できればシートの転換をすることが推奨となります。(※)
※というか、みんなやってますからね(^^;)
自分だけやらないわけにはいかないでしょう(^^;)。
スイッチバックとは?
ちなみにスイッチバックとは、いわば「人」の形をした線路であり、一旦先頭から突っ込んで、バックするという線路の形です。
東能代駅では一旦、奥羽本線の大館方面へ向かう構造・形の線路になっています。
そのため、このように
「突っ込む→バックする」
という形になっているのです。
東能代駅が、スイッチバック構造になっている理由
ではなぜ東能代駅が、スイッチバックの形になっているのか。
それは歴史の様々な要因が関係してきますので、詳しくは以下の記事をご覧ください。

東能代駅から奥羽本線で南下し、秋田駅へ
ここから秋田駅までは、奥羽本線の区間を通ります。
ただし秋田駅に着くと、奥羽本線は東・内陸部の
- 大曲
- 横手
の方面へと逃げてゆきます。
そのため、秋田駅から先・日本海沿いを南下していくには、羽越本線となります。
奥羽本線とは?
ちなみに、奥羽本線は、
- 福島
- (ここから山形県)
- 米沢
- 山形
- 新庄
- (ここから秋田県)
- 横手
- 大曲※西へ曲がる
- 秋田
- 東能代※東へ曲がる
- 大館
- (ここから青森県)
- 弘前
- 新青森
- 青森
というルートの路線です。
また、福島~新庄の区間は山形新幹線と、大曲~秋田の区間は秋田新幹線と被っています。
羽越本線とは?
また、羽越本線は、
- 秋田
- 羽後本荘
- 象潟
- (ここから山形県)
- 酒田
- 余目
- 鶴岡
- (ここから新潟県)
- 村上
- 新発田
- 新津
というルートの路線です。
それぞれ、いわゆる「旧国名」に由来する路線名
奥羽とは、以下の旧国名に由来するものです。
- 陸奥国:福島県・宮城県・岩手県・青森県
- 出羽国:山形県・秋田県
羽越とは、以下の旧国名に由来するものです。
- 出羽国
- 越後国:新潟県
参考までに、
- 出羽国:現代の秋田県、山形県
- 越後国:現代の新潟県
になります。あわせて覚えておくとよいでしょう。
「国」とは?
ちなみに「国」とは奈良時代の律令制におけるエリア分けで、現代でいう都道府県に該当します。
ただし、出羽国が秋田県・山形県の2県にまたがるように、「国」と「都道府県」が必ずしも一対一で対応するわけではありませんので、注意しましょう。
奥羽本線 東能代→秋田へ
「干拓」によってできた、八郎潟
奥羽本線をひたすら南下していくと、やがて八郎潟の東側を通ってゆきます。
八郎潟は、ヨーロッパ・オランダにヒントを得て、干拓によって出来た土地です。
そもそも、「干拓」とは?
干拓とは、元々あった湖や沼などを、堤防などを築くことによって水をわざと干上がらせて、水を無くさせて陸地を作ることです。
その新たにできた陸地に田んぼ・畑などを耕して広げ、米などの農産物の収穫をたくさん増やすことを目的としています。
戦後に干拓された八郎潟は大きな陸地となり、たくさんの米などを栽培して採れるようになりました。
オランダも、干拓によってできた国
ちなみにヨーロッパの国・オランダは、干拓によってできた土地になります。
そのため、オランダには風車がたくさんあります。
風車を回すことで、底にある水をかき集めて排水し(水を逃がし)、水が干上がって陸地ができるという仕組みになっています。
オランダに「~ダム(堤防)」という地名が多い理由
ちなみに、オランダに「~ダム(堤防)」という地名が多いのは、まさにオランダが干拓によって出来た土地であることを示しています。
千葉県の印旛沼も、干拓によって出来た土地です。
男鹿線との分岐駅「追分駅」
八郎潟をさらに南下すると、男鹿線との分岐駅である、追分駅に到着します。
「追分(おいわけ)」とは?
ここで追分とは、昔の言葉で「分かれ道」という意味になります。
その他、「交差点」のことは昔の言葉で「辻」といいます。
そして、全国他の地域には「追分」という地名や駅がたくさんあります。
例えば、北海道の「追分駅」については以下の記事をご覧ください。

長野県の信濃追分駅については、以下の記事をご覧ください。

男鹿半島と「なまはげ」
男鹿線は、秋田県の北西にのびる男鹿半島を走る路線です。
男鹿半島では「なまはげ」が 有名です。
「なまはげ」はちょっと怖いキャラクターといった感じですが、例えば怠けたりサボったりする悪い子たちを成敗する神様です。
悪い子を戒める存在「なまはげ」
なまはげは「悪い子はいねがー(悪い子はいないか)」といって、怠けたりサボったりしようとする子供の前に現れて、成敗していくのです。
こうして子供たちはなまはげを恐れて、真面目に頑張るようになります。
男鹿地方の子どもは、
といって教育されるのだそうです。
まぁ、子どもにとっては普通に怖いですよね。
秋田駅(秋田市)に到着
追分駅からさらに南下すると、土崎駅を経て、やがて秋田駅に到着します。
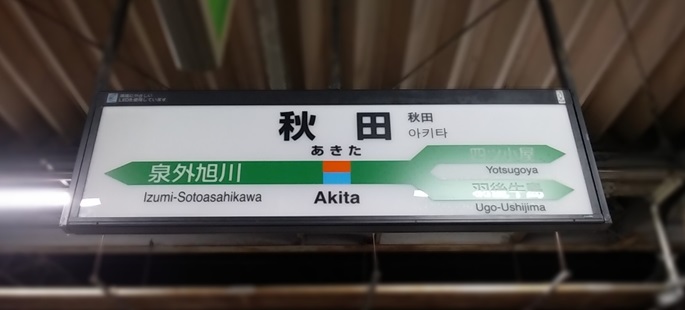
秋田駅(秋田県秋田市)
次回は、秋田の観光・歴史の話題へ
さて次回は、秋田の観光・歴史の話題について深掘りしてゆきましょう!!
今回はここまでです。
お疲れ様でした!

コメント